
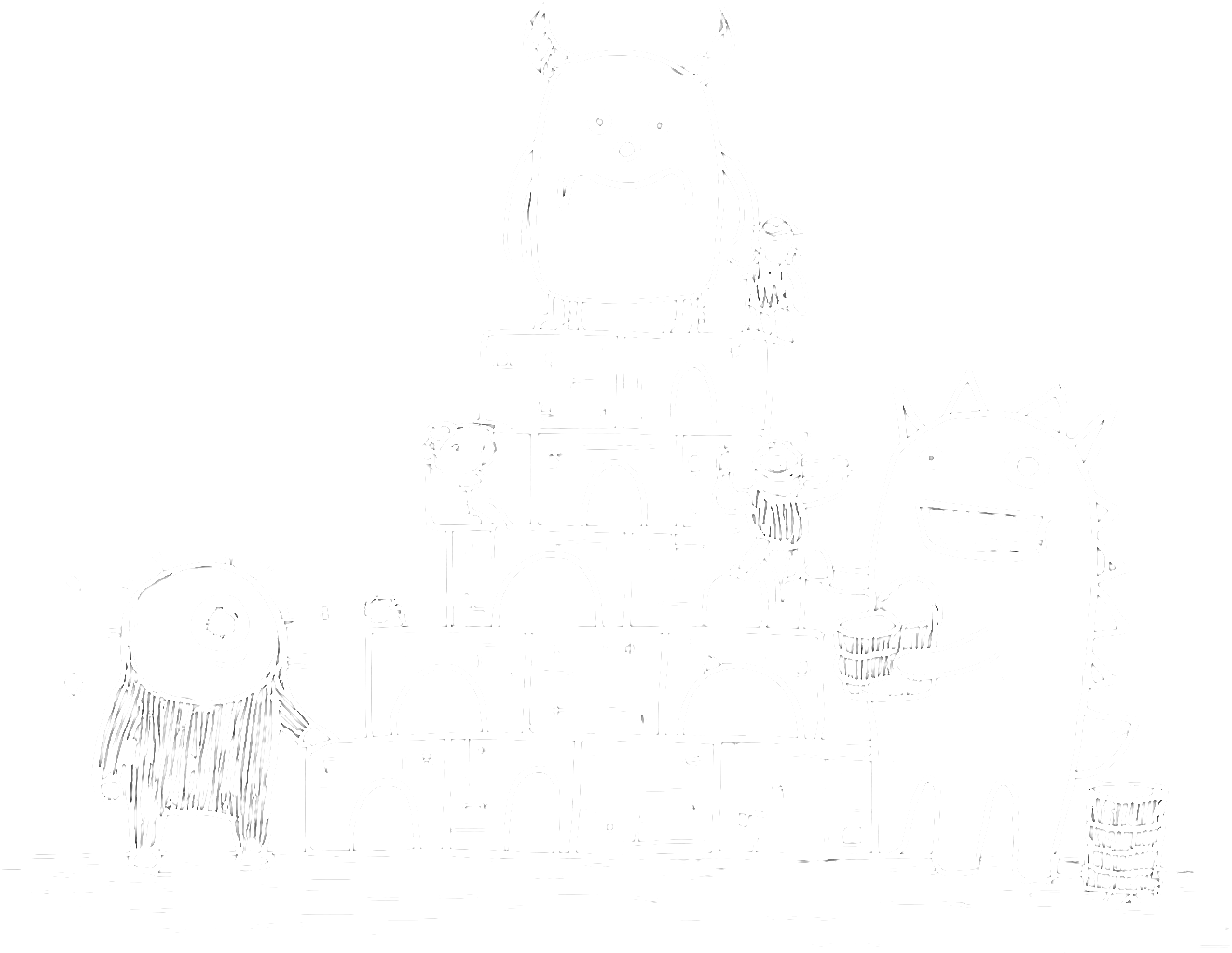
闇積奇(やみつみき) :積木の応用遊戯であり、新しいコミュニケーション方法
あなたは小さい頃「積木」をやりましたか?
あなたは今まで「闇鍋」をやったことがありますか?
「積木」と「闇鍋」をあわせた新感覚のコミュニケーション「闇積奇」について説明します。
ー 闇鍋(やみなべ)とは? ー

複数人でそれぞれ誰にも内緒で具材を持ち寄り、暗闇の中で調理して食べる鍋料理のこと。
闇積奇では、この闇鍋における「持ち寄る」と「暗闇の中」に着目しました。
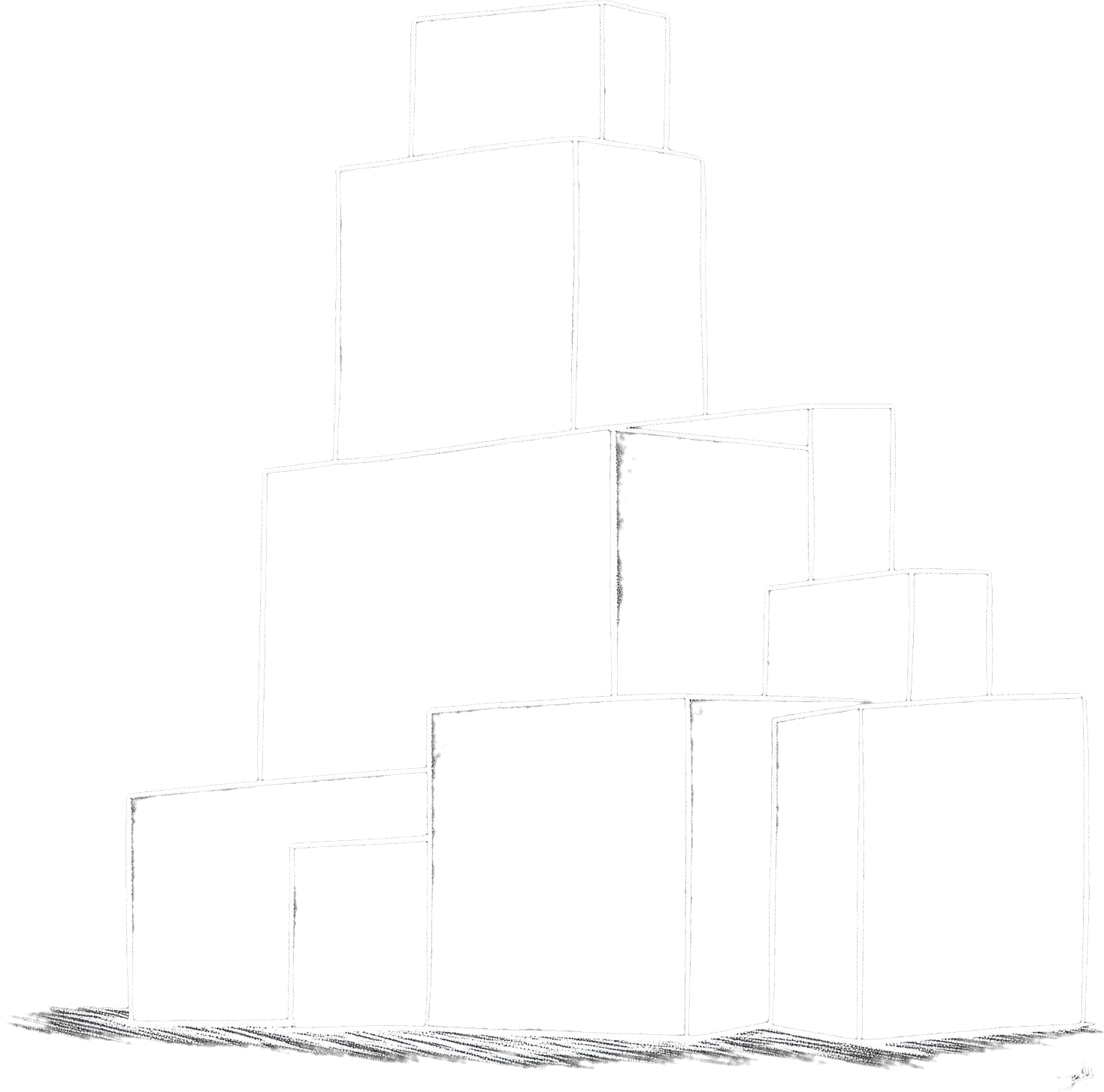
積奇≒積木
積木同様、"積むためのモノ"のことですが、思いがけない・予想外のモノを扱うため
「木」ではなく、「奇」と表記して読み方は同じく「つみき」とした造語です。
以降、このゲームでは「積奇」と呼びます。
●以下のルールに従った積奇を持ち寄って闇積奇をプレイします
・サイズ:だいたいアルミ缶サイズ以下(極端に大きかったり小さかったりしなければOK)
・積木ではなく積奇なので、材質や形状はNG↓意外であれば何でもあり。
・以下のものはNG
・怪我をしそう
・鋭利なもの、刃物
・衝撃に弱い(陶器、ガラス等)
・他のものに影響を与える
・ヌメヌメしている
・粘着質
・塗料が乾ききっていない
・匂いが強いもの
・動物(植物は虫がついておらず毒物でなければ可)
【プレイの流れ】
0.準備(前日まで)
参加者はルールに従った積奇を2~3個準備し、プレイ当日に誰にも見られない
ように持ってくる。
1.準備(当日)
主催者は準備しておいた中身が見えない1つの袋を、参加者へ回していき
全ての積奇を1つの袋に混ぜる。
2.プレイ
順番にランダムに袋から積奇を1つ取り出していく。
取り出した人は必ず前の人が置いた積奇の上に、取り出した積奇を乗せる。
取り出した積奇以外の積奇を落としたり倒したりしてしまった人が負け。
積む人以外は、積む人に対してたくさん話しかけることで集中力を低下させて邪魔する。
積む人は話しかけられた質問に対しては極力答えなければならない。
【豆知識】
●積石(積み石、ケルン)の歴史:人類最古の創造的衝動
積石の歴史は、積木の原型であり、人類の最も根源的な衝動に根ざしています。
石を積み重ねる行為は、おそらく人類が言葉を持つ以前から行われていたでしょう。
ストーンヘンジのような壮大な環状列石や、ドルメン、メンヒルといったモニュメントが
作られます。
これらは単なる構造物ではなく、天と地を結び、死者を弔い、神々と交信する聖なる空間として、
太古の人々の宇宙観や信仰を映し出していました。石を積む行為は、不安定な自然界において、
人間が秩序と意味を刻み込む最初の試みであり、そこに込められたロマンは、夜空の星々を
星座として繋ぎ合わせる営みに通じます。
積石はやがて、精度と強度を追求する建築技術へと発展します。エジプトのピラミッド、ローマの
水道橋、中世の壮麗な大聖堂、日本の石垣。これらはすべて、積み重ねるという行為の
究極形です。
積木は、積石の原理を遊びと教育に応用したものです。
近代積木のルーツは、19世紀ドイツの教育者フリードリヒ・フレーベルが考案した「恩物(おんぶつ)」にあります。
彼は、幼児期の遊びを通して、子供たちが形、空間、数といった概念を直感的に学び、
創造性を育むことを重視しました。立方体、円柱、球といった幾何学的な積木は、単なるおもちゃではなく、
宇宙の法則を内包する小さなモデルでした。フレーベルの思想は、モンテッソーリ教育など後世の教育に大きな
影響を与え、積木は世界中の子供たちの学びの友となります。
●遊びと芸術の融合:自由な創造の翼
フレーベル以降、積木は多様な形や素材に発展します。シンプルな木製の積木から、カラフルなプラスチック製のブロック(レゴなど)、さらには磁石で連結するタイプまで、素材と形状は進化を遂げました。これらは単なるおもちゃの域を超え、建築家フランク・ロイド・ライトが幼少期にフレーベルの恩物から大きな影響を受けたように、後の芸術や科学、デザインの世界に影響を与える創造性の源泉となりました。
積木は、私たちの中に眠る**「何かを創り出したい」という純粋な欲求**を解放し、無限の可能性を秘めたロマンを秘めています。
●人間の脳への影響:構造化と思考の深化
1.空間認識能力と三次元思考
ものを積み重ねることは、高さ、幅、奥行きといった三次元空間を直感的に理解する上で不可欠です。 これは、建築、エンジニアリング、デザインといった分野だけでなく、日常生活における空間把握能力の基礎となります。
2.問題解決能力と試行錯誤
どうすれば崩れずに高く積めるか、どうすれば安定した構造を作れるか、という問いは、自然と仮説を立て、実行し、失敗から学ぶという試行錯誤のプロセスを生み出します。不安定な箇所を修正し、重心を意識し、最適な配置を見つける中で、論理的思考力と問題解決能力が培われます。
3.集中力と忍耐力:
目標に向かって地道に積み重ねる作業は、高い集中力を要求します。途中で崩れても諦めずに再挑戦する忍耐力も養われます。これは、学業や仕事において不可欠な資質です。
4.創造性と表現力
決められた答えがない中で、自分のアイデアを形にする積木遊びは、無限の創造性を刺激します。頭の中のイメージを具現化するプロセスは、非言語的な表現力を豊かにします。それは、まるで宇宙に新しい星を創造するかのような、根源的な喜びを与えます。
5.脳の前頭前野の活性化
計画を立て、思考をコントロールし、目標に向かって行動する際に活性化する脳の前頭前野は、積木や積石の遊びを通して大いに刺激されます。これは、大人の集中力維持や認知機能の向上にも繋がると考えられます。
6.瞑想と集中:現代の石庭
忙しい現代社会において、大人が積木や積石に没頭する時間は、一種の瞑想となり得ます。無心で石を積み上げ、バランスを取る行為は、心が落ち着き、集中力が高まります。禅寺の石庭がそうであるように、一つ一つの石の配置に意味を見出し、その瞬間の完璧なバランスを追求することは、「今、ここ」に意識を集中させるマインドフルネスの実践であり、深い癒しと精神の安定をもたらします。
崩れることを前提とした積石は、「無常」という東洋的な美学をも体現し、そこにロマンを感じる人も少なくありません。
7.創造性の再発見:忘れていた子供の心
大人になると、私たちは「正しい答え」や「効率性」に縛られがちです。しかし、積木や積石の遊びには、正解も不正解もありません。そこにあるのは、純粋な好奇心と、自分の手で何かを創り出す喜びだけです。
子供の頃に感じた、無限の可能性を秘めた創造性を再発見する過程は、停滞しがちな大人の日常に、新しい風を吹き込むロマンティックな体験となります。
8.物理法則との対話:知的な探求のロマン
積むという行為は、常に重力や摩擦といった物理法則との対話です。大人は、子供のように感覚的に積み重ねるだけでなく、重心、モーメント、構造力学といった知識を意識的に、あるいは無意識的に活用します。
崩壊と成功を繰り返す中で、目に見えない物理の原理が、目の前のブロックを通して実感できることは、知的な探求のロマンを刺激します。
9.崩壊の美学と再生のロマン:無常と創造の循環
高く積み上げられた積木や積石は、いつか必ず崩れます。しかし、その崩壊は終わりではなく、次の創造の始まりです。崩れた破片は、次の作品の材料となり、新しいアイデアの源となります。
この**「創造→崩壊→再生」の循環**は、生命のサイクルや宇宙の摂理にも通じる、深遠なロマンを私たちに示唆します。
気になる方はX(旧Twitter)またはInstagramで私にDMください。
↓